(保険者が指定する病院等における療養の給付)
第八十四条 第六十三条第三項第二号及び第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、第七十条第一項及び第七十二条第一項の厚生労働省令の例による。
2 第六十三条第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、第七十四条の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。
3 健康保険組合は、規約で定めるところにより、第六十三条第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、第七十四条の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。
(入院時食事療養費)
第八十五条 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。
2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
5 被保険者が第六十三条第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。
6 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
7 被保険者が第六十三条第三項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。
8 第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
9 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条及び前条第一項の規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。
(入院時生活療養費)
第八十五条の二 特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから同条第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。
2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について介護保険法第五十一条の三第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。
3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。
5 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十八条、第八十四条第一項及び前条第五項から第八項までの規定は、第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。
8 85条
次の説明は、健康保険法に関する記述である。
入院時食事療養費の額は、その食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して、中央社会保険医療協議会が定める基準により算定した費用の額(その額が現にその食事療養に要した費用の額を超えるときは、その現に食事療養に要した費用の額)から、食事療養標準負担額を控除した額とする。 2011年度(平成23年度)
解答×
中央社会保険医療協議会でなく厚生労働大臣
厚生労働大臣は、この基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとされています。(健康保険法85条)
【食事療養】とは、入院時の食事の提供たる療養(特定長期入院被保険者に係るものを除く)をいう。
【特定長期入院被保険者】とは、療養病床に入院する【65歳以上】の被保険者をいう(法63条2項1号)
入院時食事療養費の額=食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した額-食事療養標準負担額
※中央社会保険医療協議会の詰問を経て定める。
現に食事療養に要した費用の額を超えるときは、現に食事療養に要した費用の額となる。
(法85)
ちなみに・・・
㋑社会保障審議会
㋺中央社会保険医療協議会
㋩地方社会保険医療協議会
に係る諮問・議決・意見を聴く場合の主語は、あくまで
【厚生労働大臣】です。㋑㋺㋩の機関が定めたり、指定したりするのではありません。
法40条、法45条、法64条、法71条、法82条、法85条、法85条の2、法86条、法88条、法92条、法124条、法160条
2 85条
次の説明は、入院時食事療養費に関する記述である。
入院時食事療養費の食事療養標準負担額は、平均的な家計の食費の状況を勘案して厚生労働大臣が定める。 2002年度(平成14年度)
解答 ○
厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に食費の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 (健康保険法 85条4項)
設問は、正しい記載となっていますが、現在の一般(減額対象者以外の被保険者)の食事療養標準負担額は、【1食につき260円】で、1日の食事療養標準負担額は、3食に相当する額を限度としています。また、被保険者に対して支給すべき入院時食事療養費は、保険者が被保険者に代わり保険医療機関に支払う現物給付の方式で行われています。
(保険外併用療養費)
第八十六条 被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、第六十三条第三項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき第七十六条第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第七十五条の二第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二 当該食事療養につき第八十五条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三 当該生活療養につき前条第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3 厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。
4 第六十四条、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条、第七十六条第三項から第六項まで、第七十七条、第七十八条、第八十四条第一項及び第八十五条第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5 第七十五条の規定は、前項の規定により準用する第八十五条第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
3 法86条1項
次の説明は、保険外併用療養費等に関する記述である。
薬事法第2条第16項に規定する治験に係る診療が行われ、当該治験が人体に直接使用される薬物に係るものであった場合は、評価療養とされる。 2008年度(平成20年度)
解答 ○
前記の通り、【評価療養】と【選定療養】は、【保険外併用療養費】として支給されますが、【保険外併用療養費】であっても、【移送費】の対象となり支給要件を満たせば、【移送費】が支給されます。
評価療養の種類は以下となります。
・先進医療(高度医療を含む)
・医薬品の治験に係る診療
・医療機器の治験に係る診療
・薬事法承認後で保険収載前の医薬品の使用
・薬事法承認後で保険収載前の医療機器の使用
・適応外の医薬品の使用
・適応外の医療機器の使用
従いまして、設問は正解となります。
薬事法第2条第16項に規定する治験(機械器具等に係るものに限る。)に係る診療は評価療養とされています。
13 法86条4項 則63条
次の説明は、療養の給付等に関する記述である。
被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等から評価療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費が支給される。この場合、被保険者に支給すべき保険外併用療養費は、その病院若しくは診療所又は薬局に対して支払うものとする。 2012年度(平成24年度)
解答○
保険外併用療養費の支払いについては、入院時食事療養費の規定を準用しており、保険外併用療養費についても現物給付として支給される。
保険外併用療養費は形式的には被保険者に支給する「償還払い」の形式を取っているが、実際は「現物給付」の取扱いが行われている。
この「現物給付」の取り扱いは、評価療養又は選定療養を行った病院又はもしくは診療所又は薬局に対して保険者が直接保険外併用療養費を支払い、この支払いがあった時は被保険者に対して入院時食事療養の支給があったものとみなすことにより行われる。(法86条4項 則63条)
(療養費)
第八十七条 保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に第七十四条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。
3 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第七十六条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第八十五条の二第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
87
【試験問題】次の説明は、療養の給付等に関する記述である。被保険者は、療養費の支給を受けようとするときは、申請書を保険者に提出しなければならない。この申請書には、療養に要した費用の額を証する書類を添付しなければならない。この書類が英語で作成されている場合には、省令の規定により、その書類に日本語の翻訳文を添付する。 【解答】○
(療養費の支給の申請)
第六十六条 法第八十七条第一項の規定により療養費の支給を受けようとする時は、被保険者は次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。
3 前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
法87条1項 則66条3項
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
被保険者又は被扶養者が海外の病院等において療養等を受けた場合に支給される海外療養費は、療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定する。 【解答】×
被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 (健康保険法 110条)
支給決定日の外国為替換算率を用いる。
海外における療養費等の支給額の算定に用いる邦貨換算率は、その「支給決定日」の外国為替換算率を用い、
「療養を受けた日の外国為替換算率を用いて算定」とした問題文は誤り。なお、海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行い、その受領は事業主等が代理して行う
法87条
【試験問題】次の説明は、健康保険法に関する記述である。
海外における療養費支給の算定となる邦貨換算率は、その療養を受けた日の外国為替換算率を用いる【解答】?
87
【試験問題】次の説明は、保険給付に関する記述である。
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等を保険者が直接当該被保険者に送金することになっている。【解答】×
その受領は事業主等が代理して行うものとし、国外への送金は行われない
現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行なわせ、その受領は事業主等が代理して行なうものとし、国外への送金は行なわないこととされている。
支給決定日の外国為替換算率を用いて算定する記述も正しい。
[自説の根拠]法87条1項、昭和56年2月25日保険発第10号・庁保険発第2号
設問は、×です。次のように修正すれば正しい記述になります。
「現に海外にある被保険者からの療養費等の支給申請は、原則として、事業主等を経由して行わせるものとし、その支給決定日の外国為替換算率(売レート)を用いて算定した療養費等は、【保険者は国外への送金は行わないため、事業主が代理受領します。】」
【試験問題】次の説明は、健康保険の保険給付に関する記述である。療養上必要のあるコルセットは、療養の給付として支給すべき治療材料の範囲に属するため、法第87条に基づく療養費により支給することとされている。
【解答】○
○療養費になるもの
・入院中を除いての医師の同意のある柔道整復師の施術
・輸血の血液
×療養費にならないもの
・補聴器
・好んで保険医以外の医師から受けた診療
療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着した時、その費用は療養費の支給対象となる。
法87条 S25.2.8保発9号 S26.5.6保文発1443号
療養費
a.保険診療を受けるのが困難なとき
〈例えば〉
1.事業主が資格取得届の手続き中で被保険者証が未交付のため、保険診療が受けられなかったとき
2.感染症予防法により、隔離収容された場合で薬価を徴収されたとき
3.療養のため、医師の指示により義手・義足・義眼・コルセットを装着したとき
4.生血液の輸血を受けたとき
5.柔道整復師等から施術を受けたとき など
b.やむを得ない事情のため保険診療が受けられない医療機関で診察や手当を受けたとき
協会けんぽHP
10 87条
次の説明は、健康保険の保険給付に関する記述である。
事業主が被保険者資格取得届の届出を怠った場合においては、その間に保険医療機関で受診しても被保険者の身分を証明し得ない状態であるので、療養費の対象となる。 2012年度(平成24年度)
解答○
設問の通り。
【参考】本問の他、無医村のため、緊急の場合に応急措置として売薬を服用したとき、国外で診療を受けた時も療養の給付等を行うことが困難であると認められ、療養費の支給対象となる。(法87条 S3.4.30保理発1089号)
被保険者が保険医について診療を受けた当時、事業主が資格取得届を懈怠していたため、当該被保険者は保険医に対し被保険者たる身分を証明し得ない状態にあったことは、法87条(療養費)の療養の給付をなすこと困難と認めたときに該当する。上記解釈のとおり正しい。本人に責任はなく、保険診療も受診することができないため、支給の対象となる。
また、実際に支給されるのは、資格取得届の提出後となる。
5 87条
次の説明は、保険給付に関する記述である。
あんま、はり、きゅうに係る健康保険の初回の療養費支給申請については、緊急その他やむを得ない場合を除いては、医師の同意書または診断書を添付する必要がある。 2005年度(平成17年度)
解答 ○
昭25.1.19保発4号より、本肢の通り。
なお、療養費支給申請書に添付すべき同意書に代えて差し支えないとされる医師の診断書は、『病名』『症状』及び『発症年月日』の明記されたものであって、保険者において療養費払の施術の対象の適否を判断できるものとされる。
医師の同意が必要な過去問として、「医師の同意により、柔道整復師の施術を受けたとき」は療養費が支給される(解答は〇)という出題があります。
㋑療養費は【同意書又は診断書】が必要(省略不可)
㋺傷病手当金は【意見書】が必要(省略可)
逆に㋑は意見書が必要なく、㋺は同意書や診断書は必要ありません。過去問に出題例あるため、確認が必要です。
(法87条、則66条、昭3保理2270号、法99条、則84条、昭3保理3163号)
12 87条
次の説明は、療養の給付等に関する記述である。
被保険者が療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に代えて療養費の支給を受けることを希望した場合、保険者は療養の給付等に代えて療養費を支給しなくてはならない。 2012年度(平成24年度)
解答 ×
被保険者が療養の給付に代えて療養費の支給を受けることを希望しても、療養費は支給されない。療養費は「療養の給付等を行うことが困難であると保険者が認めるとき」又は「保険医療機関等以外の病院等で診療等を受けたことを保険者がやむを得ないと認めるとき」のいずれかに該当する時に支給されるものである。
(健康保険法第87条第1項)
医療機関
•保険医、保険薬剤師
・保険医、保険薬剤師の登録は厚生労働大臣が行い有効期限はない。
・取り消し後5年間は登録されない。登録しない場合地方社会保険医療協議会の議を経る
・登録の取り消しは地方社会保険医療協議会に諮問する
・保険医、保険薬剤師は1月以上の予告期間を設けて登録抹消を求めることが出来る
◦みなし指定
・登録を受けた医師のみが勤務する医療機関は保険医療機関の指定がされたものとみなす
•保険医療機関、保険薬局
・開設者が申請し、指定の効力は6年で自動更新(病院(病床20以上)または病床のある診療所は該当しない)
保険医療機関(病院または病床のある診療所を除く。)または保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、その指定の効力を失う日前6か月から同日前3か月までの間に、別段の申出がないときは、更新の申請があったものとみなされる)
•指定訪問看護事業者
◦訪問看護
・居宅にて継続療養することを主冶の医師が認めた者に対して、看護師その他が行う療養上の世話、診療の補助
・看護師、保健師、助産師、準看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が行う(医師、介護福祉士は含まれない)
・介護福祉士 (1)厚生労働大臣が指定した養成施設を卒業 (2)3年以上介護等の業務に従事した者等が介護福祉士国家試験に合格
◦指定訪問看護事業者 訪問看護を行う厚生労働大臣が指定した事業者
・指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者の指定(介護保険)により「指定訪問看護事業者」(健康保険)となるがサービス事業者でなくなっても「指定訪問看護事業者」の指定は有効
•指定登録の手続き
◦地方社会保険医療協議会
登録 登録拒否 登録取消
保険機関 諮問 議を経る 諮問
保険医 -- 議を経る 諮問
◦指定
・病院、診療所、保険薬局の開設者の申請により厚生労働大臣は地方社会保険医療協議会に諮問をして指定する
◦指定の拒否
・指定(登録)の取り消しから5年未満(保険医、保険機関共通)
●健康保険法その他保健医療の法律で罰金刑(共通)
●開設者、管理者が社会保険料の滞納処分をうけ3月以上引き続き滞納(保険機関のみの理由)
・医師数、病床数の違反(一部拒否)
・申請者が地方公共団体、医療法人、社会福祉法人等でない(指定訪問看護事業者の場合のみ)
・事由該当の場合には地方社会保険医療協議会の議を経る(指定訪問看護事業者除く)
◦指定の取消
・不正請求
・地方社会保険医療協議会に諮問する(指定訪問看護事業者除く)
(中央社会保険医療協議会に諮問するのは診療報酬、食事療養費、生活療養費など)
◦指定の辞退(抹消:) ・1ヶ月以上の予告期間を設けて指定を辞退できる。
・取り消し後5年間は登録されない
•保存
・療養の給付に関する帳簿、書類、処方箋 3年
・患者の診療録 5年
被保険者
•適用事業所
◦強制適用事業所(厚生年金と同じ定義)
◦擬制的任意適用 強制適用に該当しなくなっても任意適用申請があったとみなす
◦任意適用事業所 被保険者となるべき者の1/2の同意で設立申請、被保険者の3/4の同意で適用取り消し申請
◦任意適用事業所に使用される被保険者は任意包括被保険者という
•一般の被保険者
・法人の代表は報酬を受けていれば被保険者
・5人未満の法人の代表者が業務上負傷した場合、健康保険による保険給付を行う
・個人事業主は被保険者でない
・短時間労働者 通常の就労者の所定労働時間の3/4以上であれば被保険者
・登録型派遣労働者は派遣先事業での就労状態で決定、特定労働者派遣事業に雇用される派遣労働者は派遣元事業の適用
・国、地方公共団体の職員、共済会の組合員は適用除外ではなく健康保険法の給付を行わないため保険料を徴収しない
・適用除外(適用除外該当の日の翌日に資格喪失)
◦船員保険被保険者(疾病任意継続被保険者は除外ではないが、健保被保険者となったとき船員保険被保険者の資格を喪失する)
◦日雇い(1月を超えて引き続き使用されたら被保険者)
◦臨時労働者(2ヶ月以内の期間を決めて使用される)(所定の期間を超えたら被保険者)
◦所在地が一定しない事業所
◦季節労働者(4ヶ月未満)
◦臨時の事業所(6ヶ月以内)
◦国民健保組合の事業所、
◦後期高齢者医療
・75歳到達日翌日(誕生日)に資格喪失し同日に後期高齢者医療制度の被保険者となる(75歳年齢到達時も含め資格取得時の届出は14日以内に広域連合に提出)
•任意継続被保険者
・資格喪失の前日までに2ヶ月以上(共済保険の被保険者期間除く)継続して被保険者であった者が
・資格喪失(退職または適用除外)後、20日以内に申出することで2年間
・保険者は資格喪失前の保険者(協会または組合)が管掌する(申出先も同じ)。
・船員保険、後期高齢者医療の被保険者でないこと。
◦特徴
・資格取得日は被保険者資格喪失日
・資格の得喪の確認が無い
・傷病手当金、出産手当金が無い(継続給付は可)
・保険料は全額自己負担でその月の10日までに自分で納付する(未納で即資格喪失)
・cf.(厚生年金保険第4種被保険者(任意継続被保険者)
◦任意継続被保険者の資格喪失
1~3はその翌日、4~6はその日に喪失する
1.2年経過
2.死亡
3.保険料滞納
4.当然被保険者となった
5.船員保険の被保険者となった
6.後期高齢者医療の被保険者となった
•特例退職被保険者
・特定健康保険組合の被保険者であったものが旧国民健康保険法に規定する退職被保険者であった時、当該特定保険組合に申し出る
・任意継続被保険者と近い制度で後期高齢者医療の被保険者となるまで加入できる
・国保と社保の自己負担率も同じとなった今メリットはない
退職被保険者
被用者年金制度に長期加入していた65歳未満の者(被用者保険被保険者であったことの判定を年金制度に依存するだけ)
の給付の一部を被用者保険制度が負担する制度(後期高齢者医療制度によりH26退職者が65歳になるまで存続する)
•日雇特例被保険者
•国民健康保険の被保険者 cf.国民健康保険法
◦下記以外の居住者
1. 健康保険等の職場の保険に加入している者と、その被扶養者
2. 国民健康保険組合に加入している者と、加入者の世帯に属する者
3. 生活保護を受けている者
4. 後期高齢者医療制度に加入している者
被扶養者
•生計維持(世帯主はどうか問わない)
◦配偶者(事実婚含む)、子(養子を含み継子を含まない)、孫
◦被保険者の直系尊属(曾祖父母は入るが曾孫は入らない)(養父母を含み継父母を含まない)
◦弟妹
•生計維持+同一世帯
◦3等親以内の親族
・被保険者の兄姉、3親等以内血族とその配偶者、叔父叔母とその配偶者、甥姪とその配偶者
・継子、継父母(1親等姻族となる)
・配偶者の子、父母、祖父母、兄弟姉妹、甥姪、叔父叔母
◦事実婚配偶者の父母、子(法律上姻族に当たらない)
*親等の数え方
・いとこ、甥姪の子は4親等、事実婚配偶者の祖父母、孫は対象外
◦生計維持認定
同居
130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者の1/2未満(または上回らない)
非同居
130万円未満(60歳以上、障害者は180万円)かつ被保険者からの援助より少ない
◦同一世帯
・住居、家計を共同にすること。同一戸籍か、世帯主関係を問わない
•標準報酬
標準報酬
•報酬・賞与
◦報酬の定義
・労働の対償として受ける全てのもの(臨時、3月を越える期間ごとに受けるものを除く)
◦賞与の定義
・3月を超える期間ごとに受けるもの(年4回以上支給される報酬、臨時に受けるものを除く)
◦退職金
原則:報酬、賞与に該当しない。前払いの場合、支給時期が年4回以上であれば報酬、それ以外は賞与とする
◦現物給与
地方の時価によって厚生労働大臣が決定(厚生年金保険と同じ)
労働保険料の場合、「範囲は労基署長または職安所長、評価は厚生労働大臣」
現物給与の価額の適用に当たっては、被保険者の勤務地(被保険者が常時勤務する場所)が所在する都道府県 の現物給与の価額を適用することを原則とし、派遣労働者については、派遣元と派遣先の事業所が所在する都道府県が異なる場合、派遣元事業所が所在する都道府県の現物給与の価額を適用する。(H25健保択01)
•等級 H21健保選択
・第1級¥58,000 — 第47等級¥1,210,000
3月31日の最高等級の該当者が1.5%を越える場合、等級を追加する(9月1日)が新最高等級は1%を下回ってはならない。(3月31日)
・立案は社会保障審議会の意見を聞く
cf:厚生年金「3月31日の全被保険者の標準報酬月額の平均の2倍が最高等級の標準報酬月額を越える」
標準報酬月額の決定
•定時決定
・7月1日在籍者の4~6の3ヶ月の報酬支払基礎日数が17日以上の月の平均報酬を7月10日迄に報告し、9月から適用する。
・報酬支払い基礎日数が17日未満は除く
◦定時決定を行わないケース
・6月1日~7月1日の間の資格取得(取得時決定と重なる)
・7~9月の間に随時決定の改定があるもの
◦短時間就労者の報酬月額
・3カ月とも報酬支払い基礎日数が17日未満の時(1月でも17日以上であれば通常)
・15日以上の月がある時はその月(15or16)を対象とし、ない時は従前の報酬月額
•資格取得時決定
・算定方法
◦月、週、その他一定期間の報酬
・資格取得時の報酬を期間日数で除して30倍した額
◦日、時間、出来高、歩合
・1ヶ月前に当該事業所で被保険者の同様の業務に従事した者の平均
・適用
・1/1~5/31資格取得 当年8月まで適用(9月から定時決定)
・6/1~12/31資格取得 翌年8月まで適用
•随時改定
・連続した3ヶ月著しく報酬月額が高低を生じた。
・昇給(降給)の4ヶ月後から適用し、1~6は8月まで、7~12は翌8月迄適用する。
・賃金体系の変更があった
・遡って昇給の差額が支払われた場合、差額支給月から3月(差額支給月の遡及分は除く)
・3ヶ月間いずれも支払基礎日数が17日以上
・2等級の高低
・下限上限の等級の場合
◦1級(¥63,000未満)->2級 ¥53,000未満であった
◦2級ー>1級 ¥53,000未満になった
◦46級ー>47級 ¥1,245,000以上になった
◦47級(¥1,175,000以上)->46級 ¥1,245,000以上であった
•産前産後休業・育児休業等終了時改定(H26改正)
・産前産後休業・育児休業終了日で3歳未満の子を養育する場合、事業主を経由して速やかに保険者(機構または組合)に申し出る
・終了日翌日の当月と後2月の標準報酬月額で終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定する。
・報酬基礎日数17日未満の月は除外する
・産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している被保険者は、この限りでない。
cf.産前産後休業・育児休業開始月から終了月前月までは被保険者が申し出し保険料免除
・産後休暇、介護休暇は免除なし
•保険者算定
・算定が困難な場合か著しく不当である場合
◦報酬を受けていない
◦4,5,6月の報酬支払基礎日数が3月とも17日未満
◦以前の給料の遅配、昇給差額を含む
◦休職給を含む
・低額の休職給を受けた月を除き、3月とも低額の休職給であるときは従前の報酬月額を用いる
◦賃金カットがあった 休職給の扱いと同じ
◦4,5,6月が年間平均と比べて2等級以上差があるのが常態
・前年7月から6月までの平均から標準報酬月額を算出
•標準賞与額
・賞与額を千円未満切捨て
・年度累計540万円が限度額
・事業主は5日以内に保険者等(機構、組合)に届出る
•任意継続被保険者
・資格喪失日の標準報酬月額または前年9月30日の当該任意継続被保険者の属する保険者の管掌する全被保険者の標準報酬月額の平均の低い方
•特例退職被保険者の標準報酬月額
・特定健康保険組合が管掌する前年の9月30日の特例退職被保険者以外の全被保険者の
・(標準報酬月額の平均 + 標準賞与額の平均の1/12) x 1/2(退職者に賞与はないので)
•日雇特例被保険者
・11等級の標準賃金日額
•健康保険給付
◦傷病に関する健康保険給付
療養給付
•療養の給付
・1.診察、2.薬剤、3.処置/手術、4.居宅での世話/看護、5.入院での世話/看護
・業務上外の判定途中の場合はいったん労災保険給付として業務外の時精算する
・健康保険の被保険者又は被扶養者の業務上の負傷等について、労災の給付対象とならない場合は、 原則として、健康保険の給付対象とする。(H26改正)
◦一部負担金
・端数処理 10円未満四捨五入。(医療機関から審査支払機関へは四捨五入の前)
・10円未満四捨五入 健保一部負担金、労災・雇用自動変更対象額、国民年金保険料
1.70歳の誕生月以前 3割
2.70歳の誕生月の翌月以降 1割(本来2割、軽減特例措置H26,3,31まで延長)
3.70歳以上の一定以上所得者(被保険者が) 3割
標準報酬月額28万円以上
・ただし被保険者と70歳から80歳(75歳以降「後期高齢者医療の被保険者に該当のため被扶養者で無くなってから5年間)
の被扶養者の収入合計520万円未満で1割(被扶養者がないとき383万円未満)
*被扶養者が70歳以上の家族療養費
•被保険者が70歳未満 9割
•被保険者が70歳以上 9割
•被保険者が70歳以上の一定以上所得者 7割
◦一部負担金の特例
・保険者は災害その他の特別の事情がある時、一部負担金の減額、免除、直接に徴収することとし、その徴収を猶予(6か月以内の期間)できる
◦健康保険組合の指定病院と直営病院
・指定病院では原則一部負担金は徴収するが、減額または徴収しないことを規約に出来る
・直営病院では原則一部負担金は徴収しないが、規約で徴収しないこととすることもできる
◦費用の支払い
・診療報酬(療養の給付に要する費用から被保険者が支払う一部負担金を控除した額
・社会保険診療報酬支払い基金、国民健康保険団体連合会から保険医療機関に支払われる
•入院時食事療養費
・標準的な費用から食事療養標準負担額(原則260円)の差額
・厚生労働大臣は食事療養の平均的な費用を中央社会保険医療協議会に諮問する
・食事療養費標準負担額
低所得者以外 260円
市町村民税非課税者(入院90日以下) 210円
市町村民税非課税者(入院90日超 160円
70歳以上で所得が無いもの 100円
・限度額適用認定は被保険者が保険者に申請し、保険者は期限(1年)を決めて「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付する
・被保険者は医療機関に被保険者証に添えて提出する
•入院時生活療養費
・療養病床に入院する65歳以上被保険者(特定長期入院被保険者)が受ける食事の提供および療養環境の形成(温度、給水、照明)
・標準的な費用から生活療養標準負担額(320円)の差額
・入院治療の必要性の高い者は「食費分」は食事療養費と同じで、居住費分は0円
栄養士が管理する保険医療機関 460円
上記以外の保険医療機関 420円
市町村民税非課税者 210円
70歳以上で所得が無いもの 130円
•保険外併用療養費
・原則:保険外診療があると保険が適用される診療も含めて、医療費の全額が自己負担
・「評価療養」と「選定療養」については、保険診療との併用が認められる
cf.厚生労働省「先進医療」 ◦評価医療
◦選定医療
・特別の療養環境(法63-2では被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他)
・予約診療(30分待ち限度、診療10分以上、医師40人/日以下)、時間外診療
・病床数200以上の病院の初診料、再診療(紹介なしの時)
・180日以上の入院(入院治療の必要性高い場合を除く)
・
•療養費
・保険者が療養の給付を行うことが困難であると認める場合
・療養の現物給付ができない(緊急時や地理的要因)
・やむを得ず保険医療機関以外で診療した
・事業主が取得届を怠った
・海外で受診した(為替レートは支給決定日)
・輸血の血液料金(保存血は療養の給付)
・準医療行為
◦柔道整復師の手当て(骨折、打撲、捻挫、脱臼)
・医師が診療中の場合は同意・指示した時のみ対象(ただし入院中は対象外)
◦はり、きゅう、あんま、指圧(医師の診断書、同意書が必要)
•訪問看護療養費
・保険者が必要と認める場合に支給する
・医師の指示により、居宅にて継続して療養するものが指定訪問看護による療養給付
・週3日を限度とする
・自己負担分相当額を「基本利用料」として負担する
・保険医療機関の訪問看護(医師の訪問看護含む)は療養の給付
•移送費
◦療養を受けるために緊急で移動が著しく困難な場合で保険者が必要と認める場合に支給する
・移送によって保険診療を受けることが目的
・移動が著しく困難
・緊急
◦最も経済的な通常の経路方法による移送の費用で実費以内
・医師の意見書と費用明細を提出する。
・付き添いの医師1人まで認められる
・自己負担はない
•特別療養費
国民健康保険、後期高齢者医療制度固有の給付。
被保険者資格証明書の交付を受けている場合の現金給付。
被扶養者の傷病に関する保険給付
•家族療養費
・療養費の割合
被扶養者が6歳の年度末翌日以降70歳誕生月以前 7割
6歳の年度末日以前 8割
70歳誕生月の翌月以降 本来8割 現在9割
標準報酬月額28万円以上の被保険者に扶養される70歳以降 7割
療養給付
傷病手当金
•支給要件
・(資格喪失後)特例退職被保険者でない(任意継続被保険者は可)
・療養のため継続して3日以上(支給は4日目から)労務に服することができない。
◦療養 保険給付の範囲内であればよく、実際の給付を受けている必要はない。また資格取得前の傷病によるものでも良い
◦継続して3日間
・労務不能(休業とは違う)であること。報酬の有無は問わない。所定労働時間内の(事故)による場合は当日を含める
◦労務に服することが出来ない
・本来の業務に就けないことをいい、家事副業が可能でも労務不能であるが軽労働転換により就業出来れば労務不能でない
・伝染病保菌者が隔離されたら労務不能で、労務可能であるが休業させた場合は労務不能に当たらない
•支給額
・標準報酬日額(標準報酬月額 x 1/30)x 2/3
・休日であっても「療養のため労務不能」であれば支給される
・傷病手当金支給申請所に医師の意見書、事業主の証明書を添付して保険者に提出
•支給期間
・”支給を始めた日から1年6月(資格喪失後の継続給付の場合は支給が継続しなければならない)
・労働日、休日、支給、不支給に係わらず1年6月で打ち切り
・支給期間満了後の他の疾病の併発は他の疾病単独で労務不能か判断
・船員保険法 3年、待機なし
•資格喪失後の継続給付
・資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者で資格喪失時に傷病手当金を受給している場合、傷病手当金は満了まで支給される。
・(被保険者期間に任意継続被保険者、共済組合組合員、特例退職被保険者であった期間は含まない)
・資格喪失後、任意継続被保険者である場合は支給されるが特例退職被保険者は支給されない
•他手当との調整
◦出産手当金を優先し、傷病手当金は 支給されない
◦報酬の全部または一部を受け取る時、支給されない(報酬との差額は支給)
◦障害厚生年金
・同一の傷病により障害厚生年金を支給されるとき、傷病手当金は支給されない
・(障害厚生年金 + 障害基礎年金) x 1/360の差額は支給
◦報酬と障害厚生年金 ・傷病手当金との差額が少ないほうの額が支給される
◦障害手当金 傷病手当金の合計額が障害手当金に達するまで支給しない
◦老齢年金、退職年金(退職し被保険者でない時の継続受給者に限る)
・老齢退職年金の合計 x 1/360との差額は支給
◦休業補償給付を受ける時支給されない(休業補償給付との差額は支給)
高額療養費
高額療養費
•支給要件
◦対象外の費用
・食事療養標準負担額、生活療養標準負担額、評価療養、選定療養、訪問看護療養費に関わるその他利用料
◦合算の単位
1. 個人単位 同一月、同一人、同一病院(歯科/歯科以外、入院/通院の別)
2. 世帯合算 同一月、同一世帯
•支給方法
・原則申請に基づく償還払い(全国健康保険協会には貸付金制度がある
・以下は現物給付(保険者が医療機関に支払う)
◦長期高額疾病患者
◦公費負担医療
◦同一月、同一保険医療機関、個人単位の入院医療
◦同一月、同一医療機関等(指定訪問看護事業者が含まれた)、の外来、訪問看護(H24)
・現物給付を受ける時、限度額適用認定は被保険者が保険者に申請し、保険者は期限(1年)を決めて「限度額適用認定証」を交付する
・低所得者は「限度額適用・標準負担額減額認定証」、70歳以上は「高齢受給者証」で代替
•70歳未満
・以下のの合算した額
◦a.個人
¥80,100+(医療費-¥267,000)x1%
(¥267,000の3割(¥80,100)+¥267,000を超えた金額の1%)
上位所得者(標準報酬月額53万以上)
¥150,000+(医療費-¥500,000)x1%
◦b.世帯合算
同一月、同一世帯の21,000円以上(70歳未満))の一部負担金の世帯合算額で高額療養費算定基準額を算定できる
•70歳以上
・以下のの合算した額
◦c.70歳以上の被保険者、被扶養者それぞれの外来診療(異なる病院可)の一部負担金合計が¥24,600(一般)を超える額
◦d.70歳以上の世帯員の一部負担金合計(入院診療の一部負担を含み、外来診療の高額療養費を除く)が¥62,100(一般)を超える額
•70歳未満者と70歳以上者の世帯
b + c + d で残った負担額を合算し「70歳未満高額療養費算定基準」を適用する
●高額療養算定基準額
70歳未満 70歳以上世帯合算 70歳以上外来個人
所得 A(一部負担金世帯合算) B(70歳以上負担金合算) C(70歳以上外来)
上位所得の定義 標準報酬53万 標準報酬28万 標準報酬28万
上位 150,000+(医療費-500,000)x1% 一般A 44,400
一般 80,100+(医療費-267,000)x1% 62,100 24,600
凍結期間 (44,400) (12,000)
非課税 35,400 24,600 8,000
無所得 15,000
•多数回該当
・12月に4回目(月単位に算定するので4月目と同意)からは以下を超える額
・*凍結期間中は70歳以上一般世帯合算と等しいので適用なし)
70歳未満 70歳以上
上位所得 83,400 44,400
一般 44,400 44,400(*)
低位所得 24,600 0
•長期高額疾病()内は上位所得者
・償還払いでなく現物給付なので窓口では自己負担額のみ支払う
70歳未満 70歳以上
慢性腎不全 10,000(20,000) 10,000
血友病 10,000 10,000 自己負担分は公費負担
エイズ 10,000 10,000 自己負担分は公費負担
高額介護合算療養費
•H25健保選択
•高額療養費支給額を除いた健康保険一部負担金と
介護サービス利用者負担額+介護予防サービス利用者負担額 の年間合計(前年8月から当年7月)
•健保の支給
(年間合計-介護合算算定基準額)x 介護合算按分率
介護合算算定基準額
・70歳未満を含む世帯 67万円
・70歳以上 62万円
・75歳以上(後期高齢者医療)56万円
介護の支給
(年間合計-医療合算算定基準額)x 医療合算按分率
◦傷病手当金
◦出産/死亡
出産・死亡に関する健康保険給付
埋葬料 、埋葬費
•埋葬料 cf労災:葬祭料
・死亡した被保険者により生計を維持していた埋葬を行う者に5万円
・埋葬を行う者 埋葬の事実如何に関せず社会通念上埋葬を行うべき者(行った者ではない)
•埋葬費 上記の者以外の埋葬を行った者に5万円を上限として実費
・支給対象 埋葬料、供物代、謝礼、霊柩車、祭壇費用など
•資格喪失後の給付
・資格喪失後の傷病手当金、出産手当金受給者または給付停止後3月以内に死亡した時
・資格喪失後3月以内に死亡した時支給される。
・被保険者期間要件なし、資格喪失後の傷病による死亡も可
出産育児一時金
•出産
・妊娠4月(3月+1日、12週+1日、85日)以上の分娩
•被保険者の出産1児につき39+3万円
・産科医療保障制度に加入し、H21,1,1以後であり、在胎週数22週以後の出産の場合+3万円
•支給申請
・医師、助産師の証明または戸籍届出記載事項の証明書を添付して申請所を保険者に提出
◦直接支払制度
・被保険者と医療機関が出産育児一時金の申請受取りの代理契約(申請も受取りも医療機関)をする
◦受取代理制度(H23)
・小規模医療機関が被保険者の申請した一時金を受け取る(受取りのみ医療機関)ことで事務負担を軽減
•資格喪失後の給付
・資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であった場合、6月以内に出産したとき支給される。
・(被保険者期間に任意継続被保険者、共済組合組合員、特例退職被保険者であった期間は含まない)
出産手当金
•出産の日(または予定日との早い方)以前6週42日(多胎妊娠14週98日)から出産日後8週56日の間
標準報酬日額の2/3を支給。報酬がある場合は支給なし。または差額のみ
•資格喪失後の継続給付(傷病手当金と同じ)
・資格喪失の前日まで引き続き1年以上被保険者であった者で資格喪失時に出産手当金を受給している場合、出産手当金は満了まで支給される。
・船員保険法では継続給付でなく、資格喪失後6月以内の出産で支給される
・(被保険者期間に任意継続被保険者、共済組合組合員、特例退職被保険者であった期間は含まない)
・資格喪失後、任意継続被保険者である場合は支給されるが特例退職被保険者は支給されない
•cf.産前産後休暇
被扶養者の出産・死亡に関する保険給付
•資格喪失後の支給はない
•家族埋葬料 ・死産児は被扶養者でなく、家族埋葬料は支給されない
•家族出産育児一時金
•健康保険保険料
•日雇特例被保険者

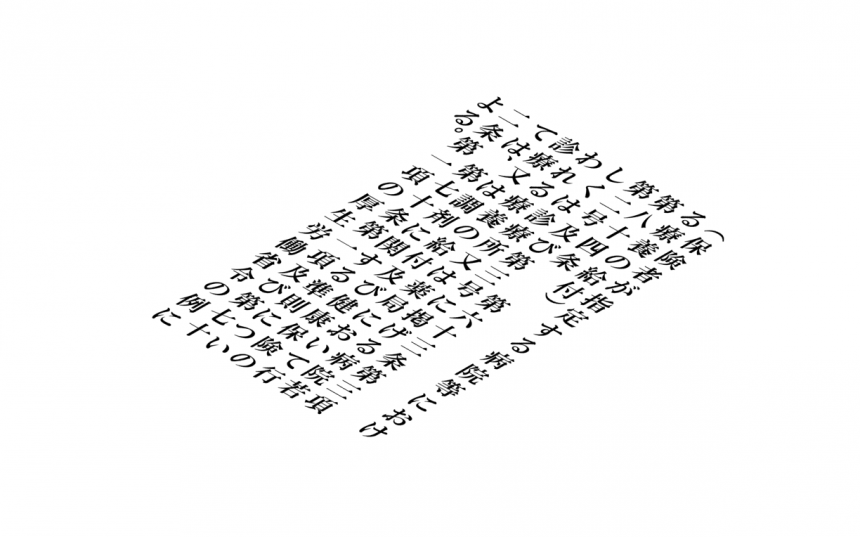
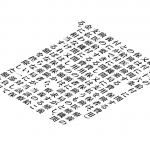

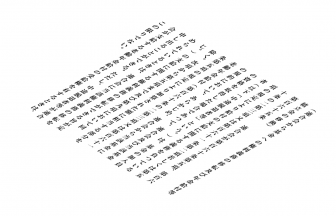
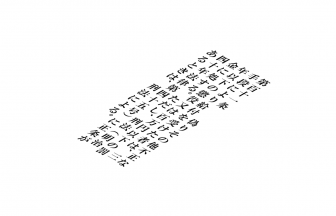
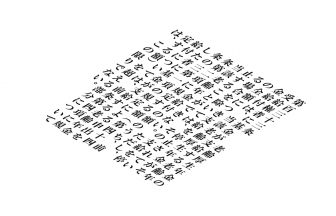
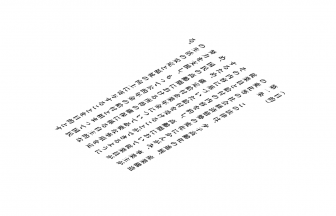
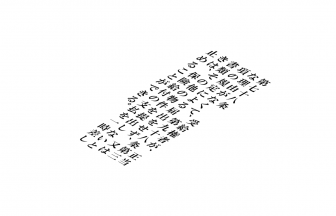
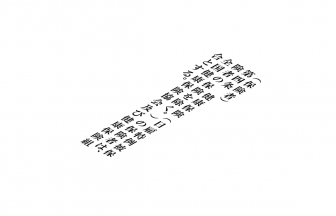


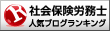




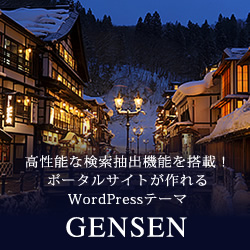

この記事へのコメントはありません。