第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
労働基準法を読んでて、32条から急に学習量と難易度がぐっと上がった感じがします。
条文の読み流しだけでは少しキツイかもしれません。
ノートがいるかもです。
第三十二条 (労働時間)
使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。工場で就業する労働者が、使用者から、作業服及び保護具等の装着を義務付けられ、その装着を事業所内の所定の更衣所等において行うものとされ、また、始業の勤怠管理は更衣を済ませ始業時に準備体操をすべく所定の場所にいるか否かを基準として定められていた場合、その装着及び更衣所等から準備体操場までの移動は、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、労働基準法上の労働時間に当たるとするのが最高裁判所の判例である。
【解答】
○
労働基準法32条の労働時間(以下「労働基準法上の労働時間」という。)とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。(三菱重工長崎造船所事件(平成12年3月9日最高裁判決))
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねることとし、かつ、労使協定により、清算期間、清算期間における総労働時間、標準となる1日の労働時間、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)及びコアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)を定めなければならない。
【解答】
×
フレックスタイム制を導入しても、コアタイムは必ず設けなければならないものではありません。全てがフレキシブルタイムという設定も出来ます。問題文のコアタイムを定めなければならないとした点が誤りです。
≪労使協定で定める範囲≫
①フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲
②清算期間(一ヶ月以内の期間に限る)
③清算期間における総労働時間(法定労働時間の総枠内で決める)
④その他厚生労働省令で定める事項
a.標準となる1日の労働時間
b.コアタイム及びフレキシブルタイムを設ける場合、その時間帯の開始及び終了時刻
問題はコアタイム及びフレキシブルタイムに関する記述を【義務】としていますが、「設ける場合」だけで定めることが義務化はされていないため間違いです。
なお、フレキシブルタイム及びコアタイムを定める場合には、その時間帯の開始及び終了の時刻を決めておく必要があります。(法32条の3、則12条の3)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める就業規則等に関する記述である。労働基準法第89条第1号により、始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項となっているが、フレックスタイム制を採用する場合には、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨の定めをすれば同条の要件を満たすものとされている。その場合、コアタイム(労働者が労働しなければならない時間帯)、フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)も始業及び終業の時刻に関する事項であるので、それらを設けるときには、就業規則においても規定すべきものである。
【解答】
×
フレキシブルタイム(労働者がその選択により労働することができる時間帯)を設けるときには、労使協定に定める、規定すべき事項です。
フレックスタイム制時に労使協定に定める事項に、
コアタイム(必ず出勤しなければならない時間帯)、
フレキシブルタイム(その時間内で自由に出社・退社して良い時間帯)
があります。
例えば、会社が9:00-17:00の勤務時間で、コアタイムを10:30-15:00(間昼休憩あり)と定めることが出来ます。フレキシブルタイムはコアタイムの前後です。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。1日6時間、週6日労働させることは、労働時間の原則を定めた労働基準法第32条の規定に反するものとなる。
【解答】
×
この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 (労働基準法 41条)
労働基準法は、労働者を守るためのもの。1日8時間
労働の基準は最低基準であり、これを上回る労働時間
(7時間とか6時間以下)は一向に差し支えありません。
労働基準法では、休憩時間を除いて1週間に40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないことになっています。翻って、問題文の例だと1週36時間、1日6時間で法定労働時間の範囲内となり、「労働基準法第32条の規定に反する」とした問題文は誤りとなります。
この問題の場合、6日間の勤務で6時間労働のため、1週間で36時間となる。1日8時間、1週間のうち40時間までなら問題ないためこの労働時間でも問題ないありません。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の解雇に関する記述である。日々雇い入れられる者については、労働基準法第20条に定める解雇予告に関する規定は適用されることはない。
【解答】
○
日雇い労働者や季節労働者など、臨時に雇い入れた以下の労働者については、原則として解雇予告は必要ありません。(法21条)
①日々雇い入れられる者
②2カ月以内の期間を定めて使用される者
③季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者
④試みの使用期間中の者
臨時採用の労働者であったとしても、当初予定した雇用契約期間を超えて、引き続き使用した場合は、解雇予告が必要となってきますので注意が必要
①「日々雇い入れられる者」は、継続勤務期間が1カ月を超えた時点で、解雇予告が必要です。
②、③「2カ月以内の期間」、「季節的業務に4カ月以内の期間」で雇用契約を結んだ労働者であっても、当初の雇用契約期間を超えて継続して使用した場合は、解雇予告が必要です。
④試用期間中の労働者であっても、雇い入れ時から14日を超えれば予告が必要となります。
たとえば試用期間3カ月で雇い入れた場合、3カ月ではなく雇い入れ時から14日を超えれば、解雇予告が必要となります。そのため試用期間中の労働者を本採用としない場合は、試用期間満了の30日前に予告することが必要です。
第三十二条の二
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第32条の2に規定するいわゆる1か月単位の変形労働時間制については、当該変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間の範囲内である限り、使用者は、当該変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる。
【解答】
×
使用者が業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような制度は、該当しません。
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1箇月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定による定め又は就業規則その他これに準ずるものにより、変形期間における各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、
変形期間を平均し週40時間の範囲内であっても使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更するような制度はこれに該当しません。
そのため、「変形期間の途中において、業務の都合によって任意に労働時間を変更することができる」とした問題文は誤りです。
なお、「法第89条第1項は就業規則で始業及び終業の時刻を定めること」と規定しているので、
就業規則においては、各日の労働時間の長さだけではなく、始業及び終業の時刻も定める必要があるとされています。
(昭和63年1月1日基発1号・ 婦発1号、平成9年3月25日基発195号、平成11年3月31日基発168号)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第32条の2等の規定によるいわゆる変形労働時間制により労働させる場合においても、同法第36条第1項ただし書の規定により、該当の有害業務については、1日について10時間を超えて労働させてはならないと解されている。
【解答】
×
前三項の規定は、第三十三条第一項の規定によつて労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第一第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 (労働基準法 61条4項)
変形労働時間制で10時間と定めた日については、12時間(10時間+2時間)を超えてはならないということです。
+2時間を超えてはいけない業務は坑内労働その他「健康上特に有害な業務」であって、
「危険な業務」ではない事に注意です。
法36条1項但書の有害業務についての労働時間延長を1日2時間までに制限する規定は、
必ずしも「1日についての法定労働時間である8時間を超える部分が対象になる」という意味ではなく、
例えば、変形労働時間制を採用している場合に、その特定日についての所定労働時間が10時間であるとするとその所定労働時間に加え2時間(この場合は12時間)まで労働させても問題ないという意味です。法36条1項但書、
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準法第36条第1項ただし書の規定によって、36協定によっても、労働時間の延長は1日について2時間を超えることはできないこととされている。
【解答】
○
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める割増賃金等に関する記述である。労働者派遣契約上、法定時間外労働及び法定休日労働がないものとされ、したがって、労働基準法第36条の規定に基づく時間外・休日労働に関する協定の締結など法所定の手続がとられていない場合であっても、派遣先の使用者が、当該労働者派遣契約に違反して法定休日において派遣中の労働者に休日労働を行わせたときは、派遣先の使用者ではなく派遣元の使用者が当該休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。
【解答】
○
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 (労働基準法 32条の4の2)
割増賃金の支払い義務は派遣元の使用者にあり、労働基準法に違反や労働者派遣契約法に違反には関係なく義務は生じます。
法違反であるかどうかにかかわらず、派遣先の使用者が派遣労働者に時間外労働・休日労働を行わせた事実がある場合は、派遣元の使用者が当該時間外労働・休日労働に係る割増賃金を支払わなければならない。(昭和61年6月6日基発333号)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める時間外・休日労働に関する記述である。派遣先の事業場において、労働基準法第36条の規定に基づく時間外労働・休日労働に係る労使協定(以下「36協定」という。)が締結され、これが所轄労働基準監督署長に届け出られている場合においては、当該派遣先の使用者は、当該事業場に派遣されて現に当該使用者の指揮命令の下に働いている派遣労働者を、当該36協定で定める内容に従い、時間外労働させることができる。
【解答】
○
変形労働時間制(労働時間等設定改善特別措置法)
・業務の繁閑に応じた始業就業時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に努める
1ヶ月単位の変形労働時間制
労使協定または就業規則で届出要
法別表1-4 運輸交通業の予備の乗員は労使協定を要しない(航空は含まれない)
労使協定または就業規則その他これに準ずるものに以下を定める
変形期間を平均して週40(44)時間を越えないこと(労使協定、就業規則)
変形期間(1ヶ月以内)、起算日、各日、各週の労働時間(勤務ダイヤ等は変形期間開始前まで)
第三十二条の三
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。)
三 清算期間における総労働時間
四 その他厚生労働省令で定める事項
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用するに当たっては、使用者は、原則として、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により一定の事項を定めて実施する必要があるが、必ずしもその事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受ける場合でなくともこの制度を採用することができる。
【解答】
○
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。
【解答】
○
フレックスタイム制の適用をうける労働者の範囲は、労使間で任意に定めることができる。そのため、フレックスタイム制を採用するために過半数代表者と労使協定を締結する必要があるからといって、その事業場の労働者の過半数がフレックスタイム制の適用を受けなければ制度を採用できないというわけではありません。
労使協定の締結は必要ですが、行政官庁への届け出は不要とされています。
≪労使協定で定める範囲≫
・ 対象労働者の範囲
・ 精算期間(1ヶ月以内)
・ 精算期間における総労働時間
・ 標準となる1日の労働時間
・ コアタイムを定める場合はその始業と終了時刻
・ フレキシブルタイムを定める場合はその開始時刻と終了時刻
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。一斉休憩の原則が適用される事業場において、労働基準法第32条の3に規定するいわゆるフレックスタイム制を採用した場合には、使用者は、その対象とされる労働者については、就業規則において、各日の休憩時間の長さを定め、それをとる時間帯は労働者にゆだねる旨記載しておけば、特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。
【解答】
×
大原則としてフレックスタイム制を適用する場合であっても、休憩時間については労働基準法第34条の要件(一斉休憩の原則等)に合致するようにしなければなりませんので、コアタイム中に休憩時間を定めます。
コアタイムの設定がない等、休憩を一斉に与えることができない場合は、労使協定を締結して、一斉休憩の適用を除外する手続きが必要です。(『特段の手続をしなくとも、休憩時間を一斉に与えなくても差し支えない。』が間違いです)
そして、休憩を取る時間帯を労働者に委ねる場合には、休憩時間の長さを定め、休憩を取る時間帯は労働者に委ねる旨を就業規則に定めます。
また、一斉休憩はすべての事業において求められているわけではなく、次の事業については、一斉に休憩を与えなくてもよいとされています。
一斉休憩の事業の種別による例外
(労働基準法40条、労働基準法施行規則31条)
1 運輸交通業(労働基準法別表第1・4号)
2 商業(労働基準法別表第1・8号)
3 金融・広告業(労働基準法別表第1・9号)
4 映画・演劇業(労働基準法別表第1・10号)
5 通信業(労働基準法別表第1・11号)
6 保健衛生業(労働基準法別表第1・13号)
7 接客娯楽業(労働基準法別表第1・14号)
8 官公署の事業(労働基準法施行規則31条)
参考:
○労働基準法 第三十四条
1 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない
○労働基準法 第四十条(労働時間及び休憩の特例)
1 別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
○労働基準法施行規則 第31条
法別表第1第4号、第8号、第9号、第10号、第11号、第13号及び第14号に掲げる事業並びに官公署の事業(同表に掲げる事業を除く。)については、法第34条第2項 の規定は、適用しない。
そもそも日本ではあまり見かけないフレックスタイム制にはこんなルールがあります。
フレックスタイム制
・労使協定と就業規則の双方
就業規則に始業終業時刻を労働者に委ねる定めをし、
下記を労使協定 届出不要
・清算期間、標準となる1日の労働時間、コアタイム、清算期間に置ける総労働時間
・精算期間は1カ月以内とし、起算日を労使協定または就業規則で明らかにする
・年次有給休暇取得の場合、標準となる1日の労働時間労働したものとする
・対象となる労働者の範囲。
・8時間/日、40(44)時間/週を越えるのは労働者の選択
・総労働時間を越えた時間は賃金を支払う。不足の勤務時間は繰越または賃金控除。
第三十二条の四
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
一 この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
二 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
三 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。)
四 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
五 その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
4 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。
第三十二条の四の二
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
1年単位の変形労働時間制
・労使協定 届出要
・ 期間の定め要
・対象期間(1カ月以上1年以内)と特定期間(繁忙期)(明記なければ特定期間なし)
・40条特例は適用しない(平均週40時間)
・対象期間内の労働日と労働日毎の労働時間を決めるが、月単位で区切って2月目以降は労働日数と総労働時間を決めておけばよい。
・2期目以降の初日30日前に過半数代表者の同意を得て書面で定める
労働政策審議会の意見を聞いて厚生労働大臣は1日、1週、1年の限度を決める
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間に関する記述である。労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、当該労働者について、当該労働させた期間を平均し1週間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(同法第33条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、同法第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければならないが、これを支払わない場合には、同法第24条違反となる。
【解答】
○
使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。
(労働基準法 32条の4の2)
ちなみに「法37条の規定の例により」とは、割増賃金の算定基礎賃金の範囲、割増率、計算方法等がすべて法37条の場合と同じことを意味します。(平成11年1月29日基発45号)
また、問題の最後の法第24条とは、賃金の支払い5原則(通貨・直接・全額・毎月1回以上・一定の期日)のことです。
【試験問題】
次の説明は、労働時間、賃金及び有給休暇に関する記述である。労働基準法第32条の4に規定するいわゆる1年単位の変形労働時間制を採用する事業場において、その対象となる労働者が対象期間中に退職した場合、賃金を清算するため、対象期間の初日から、1日8時間又は1週40時間を超える時間について、割増賃金を支払うよう賃金を計算し直す必要がある。
【解答】
○
【試験問題】次の説明は、労働基準法に定める労働時間等に関する記述である。1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
その事業場の週法定労働時間×変形期間の暦日数÷7
【解答】
○
参考: 労働基準法 32条の4第1項2号
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。
2号 対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
過去問で、変形期間の「総日数」とのヒッカケがあります。
「変形期間の暦日数÷7」とは、変形期間中の週の数です。
たとえば、25日の変形期間(1箇月以内の一定期間)であれば、週の数は約3.7週となります。
労基法では1週及び1日あたりの労働時間が原則としてあり、例外として変形労働時間制があります。
そのため、原則である1週当たりの法定労働時間を超えないようにチェックするため、週数を計算することになります。(平成9.3.25基発195号)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法の労働時間に関する記述である。1か月単位の変形労働時間制を採用した場合、変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が週法定労働時間以内となるようにするために行う、変形期間における所定労働時間の総枠の計算は、次の式によって行う。
(その事業場の週法定労働時間×変形期間の労働日数)÷7
【解答】
×
ということで、ひっかけですね。
計算式中の「変形期間の労働日数」が誤りで、「変更期間の歴日数」が正しいです。
第三十二条の五
使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、一日について十時間まで労働させることができる。
2 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
3 第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
【試験問題】
次の説明は、労働基準法に定める労働時間に関する記述である。労働基準法第32条の5に定めるいわゆる1週間単位の非定型的変形労働時間制については、日ごとの業務の繁閑を予測することが困難な事業に認められる制度であるため、1日の労働時間の上限は定められていない。
【解答】
×
1.対象
常時使用する労働者数が30人未満の
(1)小売業
(2)旅館
(3)料理店
(4)飲食店
2.適用要件
1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用するためには、適用業種に該当する事に加えて、次の要件を満たす必要があります。
(1)労使協定の作成及び行政官庁への届出
(2)1週間の労働時間が40時間
(3)1日の労働時間の上限が10時間
(4)書面による通知(下記参照)
1週間単位の非定型的変形労働時間制
フレックスタイム制との微妙な違いに注意です。
・労使協定
・届出要
・有効期間の定め不要
・何時忙しいか予め特定できない
・30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
・労働時間限度週40時間の範囲で、1日10時間まで
・当該週開始前に事前に書面で労働者に通知
・派遣労働者には適用できない
労働時間の定義が「指揮監督のもとにある時間」
休憩時間を除き1日8時間、週40時間。
暦週・・日曜日~土曜日、暦日・・午前0時~午後12時
変形労働時間制の関連法令に「労働時間等設定改善特別措置法」があります。
「業務の繁閑に応じた始業就業時刻の設定、年次有給休暇を取得しやすい環境の整備に努める」
労働基準法を読んでて、32条から急に学習量と難易度がぐっと上がってます。
条文の流し読みでは少し追いつきませんので、もう一度、フレックスタイム制と変形労働時間制について、整理します。
1ヶ月単位の変形労働時間制(32条の2)
○ 労使協定または就業規則
●届出要
○ 法別表1-4運輸交通業の予備の乗員は労使協定を要しない(航空は含まれない)
○ 労使協定または就業規則その他これに準ずるものに以下を定める
● 変形期間を平均して週40(44)時間を越えないこと(労使協定、就業規則)
● 変形期間(1ヶ月以内)、起算日、各日、各週の労働時間(勤務ダイヤ等は変形期間開始前まで)
フレックスタイム制(32条の3)
○労使協定と就業規則の双方
○就業規則に始業終業時刻を労働者に委ねる定めをし、下記を労使協定
●届出不要
●清算期間、標準となる1日の労働時間、コアタイム、清算期間に置ける総労働時間
●精算期間は1カ月以内とし、起算日を労使協定または就業規則で明らかにする
●年次有給休暇取得の場合、標準となる1日の労働時間労働したものとする
●対象となる労働者の範囲。8時間/日、40(44)時間/週を越えるのは労働者の選択
●総労働時間を越えた時間は賃金を支払う。不足の勤務時間は繰越または賃金控除。
1年単位の変形労働時間制(32条の4)
○労使協定
●届出要 期間の定め要
●対象期間(1カ月以上1年以内)と特定期間(繁忙期)(明記なければ特定期間なし)
●40条特例は適用しない(平均週40時間)
●対象期間内の労働日と労働日毎の労働時間を決めるが、月単位で区切って2月目以降は労働日数と総労働時間を決めておけばよい。
●2期目以降の初日30日前に過半数代表者の同意を得て書面で定める
労働政策審議会の意見を聞いて厚生労働大臣は1日、1週、1年の限度を決める
労働日数限度
・対象期間が3ヶ月超・・280日/年
・労働日は12日連続が限度=週1回の休日(特定期間)
労働時間限度
・10時間/日、52時間/週(隔日勤務のタクシーは16時間/日
・対象期間が3ヶ月超・・48時間を超える週は・3週連続しない かつ・3か月に3週以内
1週間単位の非定型的変形労働時間制(32条の5)
○労使協定
●届出要 有効期間の定め不要
○何時忙しいか予め特定できない
○30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店
○労働時間限度
週40時間の範囲で、1日10時間まで
○当該週開始前に事前に書面で労働者に通知
○派遣労働者には適用できない~
労働基準法の労働時間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
【試験問題】
変形労働時間制を採用せず、始業時刻が午前8時、終業時刻が午後5時である事業場において、ある労働者が午前8時から午前9時直前まで遅刻した日について、当該労働者を午前9時から午後6時まで労働させた場合、その午後5時から6時まで労働した時間については、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。なお、当該事業場における休憩時間は正午から1時間である。
【解答】
○
法37条、昭和22年12月26日基発573号、昭和33年2月13日基発90号
労働者が遅刻した場合に、その遅刻した時間分の超過労働を命じたとしても、全体の労働時間が通算して法定労働時間内であれば割増賃金の支払いは必要ない。
週の法定労働時間及び所定労働時間が40時間であって変形労働時間制を採用していない事業場において、月曜日に10時間、火曜日に9時間、水曜日に8時間、木曜日に9時間労働させ、金曜日は会社創立記念日であるので午前中4時間勤務とし午後は休業としたときは、その週の総労働時間数は40時間であるので、この月曜から金曜までについては、労働基準法第37条に基づく割増賃金を支払う必要はない。
【解答】
×
法37条
1週間の総労働時間が40時間であっても、1日の労働時間が8時間を超えている場合は、その超過時間分の割増賃金の支払いが必要になる。
問題文の場合だと、月曜日の2時間、火曜日の1時間、木曜日の1時間分が割増賃金の対象になる。
深夜業を含む業務は健康上特に有害な業務として、労働基準法第36条第1項ただし書の規定によって、36協定によっても、労働時間の延長は1日について2時間を超えることはできないこととされている。
【解答】
×
法36条1項但書、則18条
「深夜業を含む業務」は、法36条1項但書の時間外労働が1日2時間以内に制限される「健康上特に有害な業務」に含まれていない。

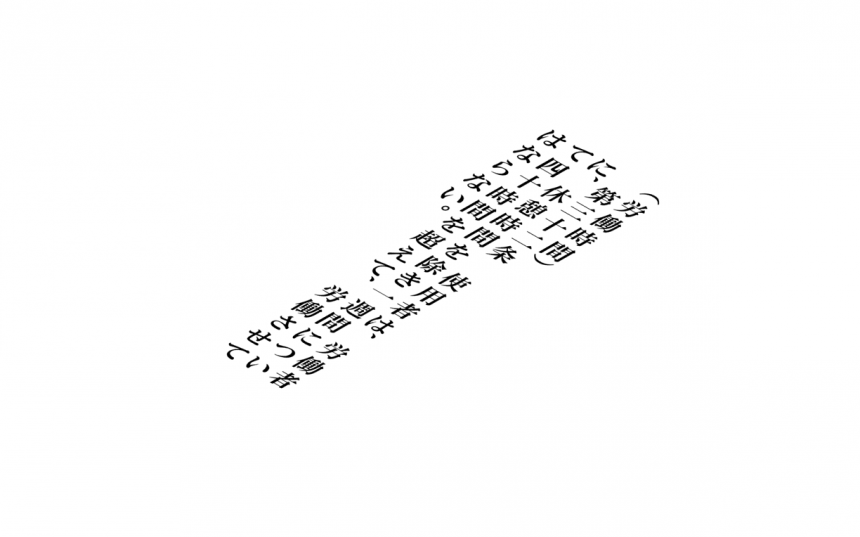

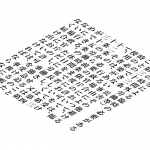
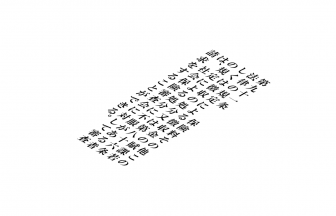
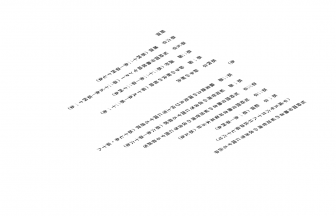
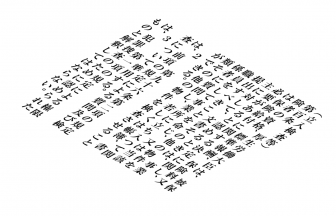
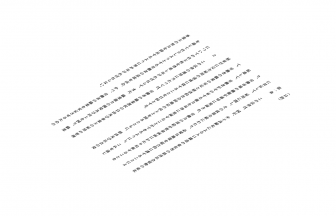

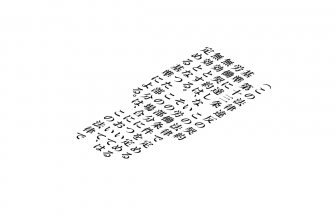








この記事へのコメントはありません。